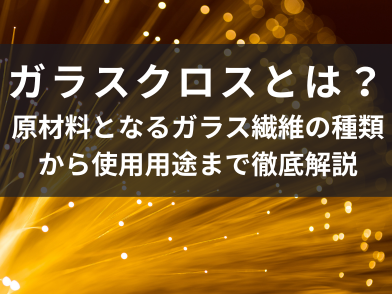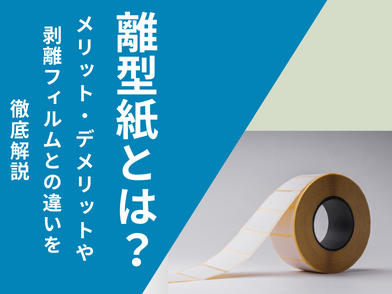サーキュラーエコノミーについて解説―実現に必要な条件とZACROS株式会社の取り組み
- コラム

SDGs(持続可能な開発目標)で掲げられている17の世界的目標には、資源を無駄なく有効に活用し、かつ循環させて社会の仕組みを持続させていく考えも含まれています。こういった循環型社会の仕組みとして、「サーキュラーエコノミー」が注目されています。サーキュラーエコノミーの意味や従来の社会の仕組みとの違い、実現のために必要となる取り組みについて実例を交えてご紹介します。
「続けていける循環」-サーキュラ―エコノミー
「サーキュラーエコノミー」は、SDGs(持続可能な開発目標)達成に向けた取り組みや、2022年4月のプラスチック資源循環法の施行によって注目されるようになった言葉です。SDGsで目指すのは、人の暮らしと環境の維持を両立し続けることを可能にする社会、そしてその実現に必要な要素のひとつが、サーキュラーエコノミーです。
サーキュラーは「円形の」「循環性の」を意味し、サーキュラーエコノミーは循環型経済と訳されます。
ここで目指す循環とは、製品の材料やその製造過程で消費される資源のサイクルを言います。製造過程や使用後に排出される廃棄物を抑制し、資源を循環させる仕組みが実現した経済モデルのことです。将来的には、廃棄物という概念が消え、原材料だけでなく製造過程で使用するものや使用中の製品も含めたすべてのものを資源として循環させる状態を目指します。
ここで重要なのは、これが経済の仕組みであるということです。個人や企業にとって経済的なメリットが生じる経済活動の一部として成立していることで、積極的かつ継続的に取り組むことが可能になります。環境配慮だけでなく経済的な循環を実現することで、持続可能な取り組みとなるという考えです。
これまでの経済モデルとの違い
経済の成長過程で行われてきた経済モデルは、大量生産・大量消費・大量廃棄を行う一方通行の直線的なシステムです。これはリニアエコノミーと言われます。
環境問題と資源枯渇が問題視されたことでリサイクルやリデュース、リユースが推奨されるようになり、リニアエコノミー+3Rのモデルが取り入れられます。
しかし、この方法でも資源消費・廃棄はなくならず、持続性が高いとは言えません。そこで、廃棄をなくし完全な循環を目指すサーキュラーエコノミーが提唱されました。従来の直線状の経済であるリニアエコノミーと異なり、資源から生産されたものが再び資源として循環する環状の経済がサーキュラーエコノミーです。
サーキュラーエコノミーを実現するための条件
サーキュラーエコノミーを実現する基本的な条件としては次のようなものが提唱されています。
- 3Rの取り組み強化
リデュース・リサイクル・リユースをそれぞれ強化することで、輪をつなげた状態に近づけることができると考えられています。 - 資源投入量と消費量の抑制
投入した資源に対してリサイクル量が釣り合わないと、直線的な経済かつ逆ピラミッド状のリニアエコノミーに近づきます。資源投入量と製品の消費量を抑制し、バランスよく循環できるようにする必要があります - ストックの有効活用
そのときの経済状況や世界情勢によっても、必要となる投入資源や販売量、製品の使用量には波があります。こういった増減の波を吸収できるような資源ストックの仕組み作りが必要です。 - 付加価値の創出・増大
サーキュラーエコノミーを持続可能なものとするためには、価値を創出し経済活動の一部として成立させる必要があります。使用後の製品をリサイクルした原料や製品、またはその加工過程自体に価値を生み、すでにそこに経済活動が伴っている場合は、その価値を最大化させる仕組み作りが求められます。
このように価値を大きくすることで、リサイクルに費やした生産コストも回収でき、経済活動として成立するようになります。 - 自然のシステムを再生
イギリスに本部を置き、早くからサーキュラーエコノミーの推進に取り組むエレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーの原則のひとつとして自然システムの再生を提唱しています。
自然界に存在する循環の仕組みを再生し、再び機能させることで自然資源を保存、または増加させ、サーキュラーエコノミーの循環も実現します。
期待される効果
- 資源消費の最小化と環境安定
石油由来の天然資源の消費が最小化されるため、CO2排出量の削減にもつながり、脱炭素社会の実現に寄与します。 - 廃棄物の発生抑止
現在は適切な処理がされずにごみとなってしまう「廃棄物」をも再使用することで廃棄物そのものをなくします。これにより、今も発生しているプラスチックごみの排出も抑止されます。 - ビジネスの新たな競争力
サーキュラーエコノミーの実現により、資源の循環に関する新たなビジネスモデルが創出され、経済的メリットを伴う循環のシステムが確立されます。こういった新たなビジネスモデルを構築することで、ビジネスにおける競争優位性の確保につながります。
取り組みは項目ごとに個別の目標を定めて
これらのサーキュラーエコノミー実現に向けた取り組みは、すべてを同時に推し進めるのではなく、それぞれについて個別に取り組んでいくことが有効です。
企業がサーキュラーエコノミーへの転換を進める場合、企業の経営活動を続けながら新たな取り組みを進めなければなりません。現状でビジネスとして成立しているシステムを継続しながら転換を進める必要があり、すべてを同時に100%にすることは困難です。
上記で紹介した条件のひとつ、またはいくつかに目標を定めて、部分的に取り組みつつ全体の効果へとつなげていくことで、サーキュラーエコノミー実現を目指します。
ZACROS株式会社の環境対応事例
単素材詰め替えパウチ「モノマテリアルパウチ」
循環型社会への貢献として、ZACROS株式会社は2030年までに廃棄物量30%削減を目標に取り組みを行っています。その内のひとつとして、リサイクルが容易で、従来の複合素材が持つ、強度物性、各種バリア性を備えたPEモノマテリアルスタンディングパウチの開発に国内で初めて成功しました。
粘着剤燃料化システム「ゲル燃焼ボイラー」
ここからは「リニアエコノミー+3R」の取り組みにはなりますが、環境負荷低減と経済性を両立させた実例をご紹介します。
産業向けや家庭用などのテープ類に使用される粘着剤は、一度固化が始まれば液状に戻ることはなく、凝固した粘着剤の大半が産業廃棄物となっているばかりか、処理費用も甚大です。
現状でも、固化させる前の液状の粘着剤を燃料とする技術はあり、固形でも特殊な装置を使うことで燃料化することは可能です。しかし、液状と固形が混ざった状態の粘着剤を燃料とするのは技術的に別のプロセスを必要とするため、普及は進んでいません。
ZACROS株式会社はそこに着目し、資源の有効活用の一環としてゲル燃焼ボイラーを開発しました。
このゲル燃焼ボイラーでは、固化する前の粘着剤の状態を長く保つような処理をしながら燃焼させることが可能です。完全燃焼するため黒煙や一酸化炭素が発生せず、地球環境と周辺環境に配慮した処理が可能です。
また、このボイラーで粘着剤を燃焼した際に発生する熱は、回収して工場のエネルギー資源として再利用することが可能です。蒸気としてそのまま活用する方法や、熱回収発電装置と組み合わせることで、簡易的な火力発電が可能になり、電気エネルギーとしての再利用もできます。
ゲル燃焼ボイラーは事業所単位で設置できるようコンパクトに設計されています。これまでは廃棄または別施設において処理されていた粘着剤廃液を、自社に設置したゲル燃焼ボイラーにより処理できるようになり、輸送に関する燃料の抑制ができトータルCO2排出量の削減にもつながります。
ZACROS株式会社では、持続可能な循環型の経済を実現する取り組みとして、ゲル燃焼ボイラーをご提案しております。
ゲル燃焼ボイラーに関するお問い合わせは下記よりご連絡ください。
CONTACT お問い合わせ
事業・商品・サービスに関して
お気軽にお問い合わせください。
3営業日以内にご連絡いたします。